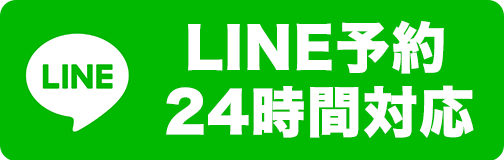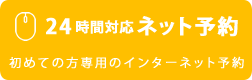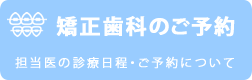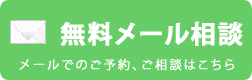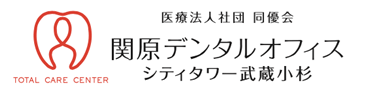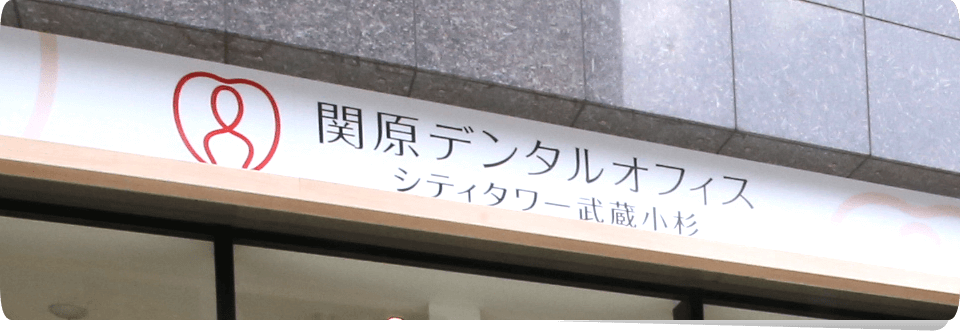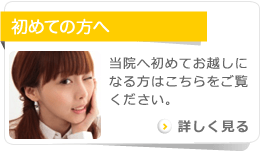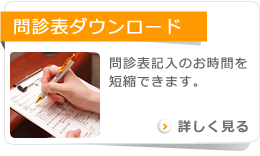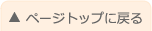今日は加藤先生が休日どう過ごされているのか、また、今後の目標について聞きたいと思います。
今日は関原デンタルオフィスの歯科医師、加藤先生にインタビューさせて頂きました。
加藤先生には、休日をどう過ごされてるのか、また当院歯科医師としての今後の目標についてお聞きしました。
<休日の過ごし方について>
朝早くに起きて読書する時間が好きです。
学生時代、サッカー部に所属していたので、その仲間と今でもたまにサッカーする時もあります。
当時は2年間キャプテンを務めさせていただいて、自分なりにチームを引っ張ってまとめられたかなとは思います。
本当に上下関係がない部だったので、選手同士もすごく仲が良かったです。
試合中でも言いたいことは言える仲だし、ピッチ外でも一緒にしゃべったり、ご飯に行ったりといった仲になっています。
<今後の目標について>
以前は藤沢市民病院に勤めていたのですが、今でも月曜日だけあちらに顔を出しています。
比較的難しい抜歯なども安心していただけるよう、今でも抜歯の技術は磨いていきたいと思ってます。
朝はスタッフの皆さんよりちょっと早めに出勤して、勉強だったり、自分の技術不足のところを補っています。
後は関原院長に、治療方針・治療検査などを聞いて、アドバイスいただくことも多々あります。
まだこちらに入って間もないので、前に診させていただいたドクターの引継ぎをしっかり行って、患者様に不安を感じさせないよう寄り添いながら治療を進めていきたいと思っております。
日付: 2020年11月16日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ