こんにちは
関原デンタルオフィスです。
2月17日(火) 午前
こちらを休診とさせて頂きます。
14時30分より通常通り診療致します。
また、
望月先生 9日(月) 10日(火) 12日(木)
輿先生 7日(土)
不在とさせて頂きます。
ご不便お掛け致しますが、
ご理解の程よろしくお願い致します。
日付: 2026年1月15日 カテゴリ:お知らせ
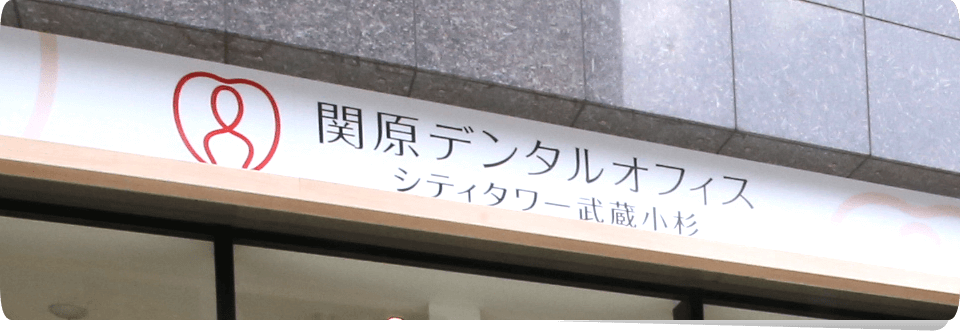
こんにちは
関原デンタルオフィスです。
2月17日(火) 午前
こちらを休診とさせて頂きます。
14時30分より通常通り診療致します。
また、
望月先生 9日(月) 10日(火) 12日(木)
輿先生 7日(土)
不在とさせて頂きます。
ご不便お掛け致しますが、
ご理解の程よろしくお願い致します。
日付: 2026年1月15日 カテゴリ:お知らせ
こんにちは。
関原デンタルオフィスです。
新しい一年が始まり、気持ちも新たにスタートされている方も多いのではないでしょうか。
実は、新年はお口の健康を見直すのにとても良いタイミングです。一年の始まりにお口の中をしっかり整えておくことが、これからの健康を守る第一歩になります。当院では、新年のスタートに合わせて“歯の健康チェック”としての定期検診をおすすめしています。毎日の歯みがきだけでは落としきれない汚れをすっきりと取り除き、むし歯や歯周病などのトラブルを早期に発見することにもつながります。今回は、新年の口腔ケアに役立つお口の健康チェックと唾液検査についてご紹介します。
当院の定期検診では、従来の器具による歯石除去に加え、エアフロー(AirFlow)を活用したクリーニングを行っています。エアフローとは、微細なパウダーをジェット水流で吹き付けることで、歯の表面にこびりついたバイオフィルム(細菌の膜)、ステイン(着色)、初期の汚れまでを効果的に除去する機器です。
ブラシでこする必要がないため、歯や歯ぐきへの負担が少なく、短時間でツルツルの仕上がりになります。「痛みが苦手」「一度でしっかりきれいにしたい」という方にも人気の高いクリーニング方法です。年末の忙しい時期こそ、効率よくきれいにできるエアフローは大変おすすめです。
さらに当院では、今年より唾液検査システム「シルハ(SillHa)」を導入しました。
短時間で測定でき、むし歯・歯周病のリスクを“数値”で確認できるため、より科学的で精密な予防ケアが可能になります。唾液検査でわかる主な項目は以下の6つです。
① むし歯菌の量
むし歯菌が多いほど酸をつくりやすく、むし歯の発生リスクが高くなります。
② 酸性度(pH)
食後は口の中が酸性になり、歯が溶けやすい環境になります。酸性度が低い(強い酸性)ほどむし歯の危険が高まります。
③ 緩衝能(中和力)
酸性に傾いた口内を中和する力です。緩衝能が弱いと、ダメージを受けた歯が再石灰化しにくくなります。
④ 白血球数
口腔内の炎症の指標になります。歯ぐきの腫れや歯周病のサインが数値として確認できます。
⑤ タンパク質量
歯ぐきからの出血や炎症があると値が上昇します。歯周病の早期発見に役立ちます。
⑥ アンモニア量
口臭や歯周病菌の活動性と関連します。高い値は歯周組織の状態に注意が必要です。
これらの項目を総合的に評価することで、「むし歯になりやすいタイプなのか」「歯周病リスクが高い理由は何なのか」といったことが具体的にわかります。数値で“見える化”されるため、ご自身の口の状態をより理解しやすくなるのも特徴です。
検査後は歯科医師・歯科衛生士が丁寧に解説します。
唾液検査の結果は、歯科医師と歯科衛生士が詳細に分析し、お口の状態と合わせて総合的に説明します。例えば同じ「むし歯ができやすい方」でも、原因は人によって異なります。
このような違いを理解することで、より効果的なセルフケア方法を選ぶことができます。また当院では、検査結果に基づき、患者様それぞれのリスクに合った歯磨き粉・洗口液・補助用具などを処方しています。「なんとなく選んでいる」ケア用品を、より自分に合ったものに変えるだけで、予防効果は大きくアップします。
年末年始はどうしても食生活が乱れやすく、むし歯や歯周病が進行しやすい時期です。
甘いものや間食が増え、帰省や旅行でブラッシングが不十分になることも多く、トラブルを抱えたまま新年を迎えてしまう方も少なくありません。今年のうちに一度、お口の環境をリセットし、来年も健康な状態を保てるように整えておきましょう。エアフローでのクリーニングや検診、唾液検査についても、どうぞお気軽にお問い合わせください。
✨✨ご予約をご希望の方はこちらからクリックしてください✨✨
日付: 2026年1月15日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ
こんにちは
関原デンタルオフィスです。
1月15日(木) 午前
こちらを休診とさせて頂きます。
14時30分より通常通り診療致します。
また、
望月先生 19日(月) 午前中のみ
不在とさせて頂きます。
ご不便お掛け致しますが、
ご理解の程よろしくお願い致します。
日付: 2025年12月9日 カテゴリ:お知らせ
こんにちは
関原デンタルオフィスです。
12月28日(日)〜1月4日(日)まで 休診とさせていただきます。
12月27日(土)は14時00分まで診療しております。
年始は1月5日(月)10時から 通常通り診療開始致します。
ご不便をお掛けしますが、
ご理解の程よろしくお願い致します。
日付: 2025年12月9日 カテゴリ:お知らせ
こんにちは
関原デンタルオフィスです。
お子様の乳歯が生えはじめると、「そろそろ歯みがきを始めた方がいいのかな?」と気になり始める保護者の方も多いのではないでしょうか。
お子様の大切な歯を守るためには、毎日の仕上げみがきと、乳歯の時期に合わせたケアが欠かせません。しかし、成長とともに「イヤイヤ期」に入ると、歯みがきを嫌がることも増え、悩まれる方も少なくありません。
今回は、歯みがきのスタート時期から、イヤイヤ期を乗り越える工夫、仕上げみがきのコツまで、親子で前向きに取り組める方法をわかりやすくご紹介します。
乳歯が1本でも生えたら、お口のケアはスタートしてOKです。最初は歯ブラシを使わず、濡らしたガーゼで優しく拭くことから始めましょう。
歯が2〜3本と増えてきたら、赤ちゃん用のやわらかい歯ブラシに切り替えて、1日1回、夜の寝る前を目安に「仕上げみがき」を行っていきます。
この時期は「歯みがき=痛くない」「怖くない」と感じてもらうことが大切です。無理をせず、お子様のペースに合わせながら、遊び感覚で慣らしていきましょう。
2歳半~3歳頃には、上下10本ずつ、計20本の乳歯がほぼ生えそろいます。この頃から、奥歯や歯と歯の間のケアが特に重要になります。
歯ブラシの毛先を使って1本ずつていねいにみがくことが大切です。自分でみがく練習も始められますが、夜は必ず仕上げみがきを行いましょう。
親子で一緒にみがいたり、好きな歯ブラシや歯みがき粉を選ぶなど、「楽しめる工夫」で習慣化を目指します。
3歳ごろから始まる「イヤイヤ期」には、歯みがきを強く嫌がるお子様も少なくありません。無理に押さえつけてしまうと、かえって歯みがき嫌いになってしまうことも。
この時期は、無理強いせず以下のように「楽しい時間」に変える工夫が効果的です。
◎歌をうたう/歯みがき動画を一緒に見る
◎お気に入りのぬいぐるみに「先にみがこうね」と声をかける
◎歯みがき後に「よくできたね!」とほめてあげる
◎嫌がる日は「1か所だけ」「10秒だけ」と区切る
完璧を求めず、「少しでもできたらOK」と思うことが、続けるコツです。
仕上げみがきをするときは、姿勢や手順を意識するだけで、負担が減りスムーズになります。
・お子様の頭をひざの上にのせる「寝かせみがき」が基本
・歯ブラシはペン持ちで優しく、力を入れすぎない
・歯と歯ぐきの境目、奥歯の溝、裏側をていねいに
・順番を決めて磨くと、みがき残しを防げます
「寝かせみがき」は視野が確保でき、安定感があるためおすすめです。
仕上げみがきに加えて、歯を強くするための「フッ素塗布」や、歯科医院での「定期検診」も重要です。特に乳歯や生えたての永久歯はむし歯になりやすいため、3か月ごとのフッ素塗布が効果的とされています。また、仕上げみがきでは落としきれない汚れや歯の生え方の異常なども、歯科でチェックできます。「むし歯になる前に防ぐ」ことが、お子様の将来の歯の健康につながります。
仕上げみがきは、お子様の歯を守るための大切な習慣です。スタート時期やイヤイヤ期の対応に悩むこともあるかもしれませんが、大切なのは“毎日の積み重ね”です。
当院では、お子様の成長に合わせたケアのご相談や、フッ素塗布・定期検診も行っております。小さな頃から通っていただくことで、歯医者さんへの不安も少なくなります。
「どんなふうに仕上げみがきすればいい?」「歯みがきを嫌がるけど大丈夫?」といったお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
日付: 2025年12月1日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ
こんにちは
関原デンタルオフィスです。
12月9日(火) 午前
こちらを休診とさせて頂きます。
14時30分より通常通り診療致します。
また、
望月先生 13日(土) 終日
輿先生 20日(土) 終日
不在とさせて頂きます。
ご不便お掛け致しますが、
ご理解の程よろしくお願い致します。
日付: 2025年11月18日 カテゴリ:お知らせ
こんにちは
関原デンタルオフィスです。
「エアフローって聞いたことはあるけれど、普通の歯のクリーニングと何が違うの?」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。エアフローは近年注目されている、歯の表面をやさしくきれいにできる新しいクリーニング方法です。
今回は、エアフローのしくみや通常のクリーニングとの違い、期待できる効果や注意点について、わかりやすくご紹介します。
エアフローは、微細なパウダーと水・空気を同時に噴射することで、歯の表面や歯ぐきまわりの汚れをやさしく除去するクリーニング方法です。
使用するパウダーには、グリシンやエリスリトールなど体にやさしい成分が使われており、粒子が非常に細かいため、歯面や歯と歯の間、被せ物のすき間などの細かい部分にも入り込みやすいのが特徴です。
また、従来のように金属の器具でガリガリ削るのではなく、吹きつけるように除去するため、歯や歯ぐきへの刺激も少なめです。
どんな効果がある?
エアフローでは、次のような効果が期待できます。
・着色汚れの除去
・バイオフィルムの除去
・歯面のツルツル感
・インプラントや矯正中の清掃にも対応
見た目の改善だけでなく、むし歯や歯周病の予防にもつながるのがエアフローの魅力です。日々のケアでは落としきれない汚れをやさしく取り除き、清潔なお口の環境を保つサポートをしてくれます。
従来のクリーニング(スケーリング)は、歯石を専用の器具で削って落とす方法です。金属製のチップやブラシを使うため、歯石や深い部分の汚れには効果的ですが、着色や細菌の膜(バイオフィルム)の除去には限界があります。
一方、エアフローは、微粒子を吹きつけて汚れをやさしく取り除く方法です。削る感覚がほとんどなく、音や振動も控えめなため、「ガリガリが苦手」「刺激が怖い」と感じる方にも受け入れられやすい特徴があります。
なお、歯石が多い場合は、エアフロー単独では不十分なこともあり、スケーリングと組み合わせて行うこともあります。
エアフローには、次のようなメリットがあります。
◎歯を傷つけずにやさしく汚れを除去できる
◎施術中の痛みや不快感が少ない(個人差あり)
◎歯の表面が明るくなり、見た目も清潔感アップ
◎通常のブラッシングでは落としにくい細かな部分までアプローチ可能
◎処置時間が比較的短く、負担が少ない
とくに、「ホワイトニングまでは考えていないけれど、着色汚れは気になる」という方にとって、自然な歯の明るさを取り戻すケアとして人気があります。
エアフローは比較的安全性の高い施術ですが、以下のような点には注意が必要です。
・パウダーの成分にアレルギーがある方は事前に要相談
・歯石が多い方や歯周病が進行している場合は別の処置が必要になる可能性あり
また、医院ごとに使用している機種やパウダーの種類が異なる場合もあるため、気になる方はあらかじめスタッフにおたずねください。
エアフローは、歯を削ることなく、やさしく・しっかり汚れを落とせるクリーニング方法です。着色や細菌のかたまりを除去し、歯を本来のツルツルした状態に近づけることで、むし歯や歯周病の予防にもつながります。
通常は自費で行われることの多いエアフローですが、当院では保険診療内でご案内しております。
患者様のお口の状態に応じて、エアフローによるケアをご提案しておりますので、「歯をきれいにしたいけど、削られるのはちょっと苦手…」「着色汚れが気になる」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
日付: 2025年10月21日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ
こんにちは
関原デンタルオフィスです。
11月6日(木) 午前
11月18日(火) 午前
こちらを休診とさせて頂きます。
14時30分より通常通り診療致します。
また、
院長先生 25日(火) 午前
早田先生 15日(土) 終日
望月先生 8日(土) 終日
輿先生 15日(土) 終日
不在とさせて頂きます。
ご不便お掛け致しますが、
ご理解の程よろしくお願い致します。
日付: 2025年10月9日 カテゴリ:お知らせ
こんにちは
関原デンタルオフィスです。
寝ているときや日中、無意識に歯をぐっと噛みしめていませんか?実は“くいしばり”は、歯や顎に大きなダメージを与えるクセのひとつです。
歯ぎしりやくいしばりは、誰にでも起こり得る身近な習慣ですが、自分では気づきにくいことも多く、知らず知らずのうちに歯や顎に大きな負担をかけていることがあります。今回は、「くいしばり」の種類や原因、放置するリスク、そして対処法について、分かりやすくご紹介します。
くいしばりは、上下の歯を強く噛みしめる無意識の習慣で、医学的には「ブラキシズム(歯ぎしり)」と呼ばれる行為のひとつです。
睡眠中だけでなく、日中の作業中やストレスを感じたときにも起こることがあります。正常な状態では、上下の歯は軽く閉じていても接触していないのが自然です。
しかし、くいしばりが習慣化すると、長時間にわたって強い力が歯や顎にかかり、さまざまな不調を引き起こす原因になります。
歯ぎしり・くいしばりには3つのタイプがあります
くいしばりは一括りにされがちですが、実は3つのタイプに分けられます。
くいしばりは、日常のささいな習慣や体の状態が引き金になることがあります。放置すると、歯や顎への影響だけでなく、全身の不調につながることもあるため注意が必要です。
【主な原因】
・ストレスや緊張
・集中時のクセ
・噛み合わせや顎のズレ
・睡眠の質の低下や呼吸の乱れ
【放置すると起こるトラブル】
・歯のすり減りや欠け、詰め物の破損
・顎関節症(口が開きにくい、カクカク音がする)
・頭痛や肩こり、首の張り
・知覚過敏や歯ぐきの退縮
長期的には、歯だけでなく顎関節や周囲の筋肉にも影響を及ぼすため、早めの対処が大切です。
◎ナイトガード(マウスピース)の装着
くいしばり対策としてよく使われるのが、「ナイトガード」と呼ばれるマウスピース型の装置です。就寝時に装着することで歯と歯の接触を防ぎ、歯のすり減りや顎への負担を軽減します。
ナイトガードには「ハードタイプ」「ソフトタイプ」などがあり、症状や装着感の好みに合わせて選べます。
◎生活習慣の見直しとストレスケア
・日中は「上下の歯を離す」意識をもつ
・姿勢を整え、首や肩の緊張をゆるめる
・ストレッチや深呼吸でリラックスする
・睡眠をしっかりとり、心身を休める
くいしばりは、ナイトガードだけで完全に解決するとは限らず、生活面からのアプローチも重要です。
くいしばりや歯ぎしりには、「クレンチング」「グラインディング」「タッピング」といった種類があり、それぞれが歯や顎に負担をかける原因となります。
放置するとさまざまな不調を引き起こすため、ナイトガードの活用や生活習慣の見直しによって、早めの対処を心がけましょう。
当院では、くいしばりに関するご相談やナイトガードの作製も行っております。「もしかしたら…」と心当たりのある方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
日付: 2025年9月30日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ
こんにちは
関原デンダルオフィスです。
10月9日(木) 、10月21日(火)の午前の診療を
休診とさせて頂きます。
14時30分より通常通り診療致します。
また、
関原先生 14(火) 終日
望月先生 4(土) 終日
輿先生 25(土) 終日
不在とさせて頂きます。
ご不便お掛け致しますが、
ご理解の程よろしくお願い致します。
日付: 2025年9月30日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ